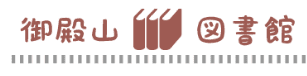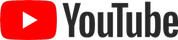INFORMATION
お知らせ
2025-04-19
2025-04-19
オススメ無料没後60年記念矢野橋村展関連企画 マナビスト講座:もっと知りたい枚方ゆかりの美術家たち 講演『近藤尺天と浪華の文人たち』[広報・SNSのお知らせ]
2025-04-15
WorkshopNEWOPEN ATELIER「"物語"をひらく」 シルクスクリーンでアートフラッグをつくる(全5回)[広報・SNSのお知らせ]
2025-04-15
重要NEW令和7年度 用紙類販売料金の決定について[各種サービスのお知らせ]
2025-04-06
ExhibitionWorkshop御殿山生涯学習美術センター企画展 没後60年記念 矢野橋村展[広報・SNSのお知らせ]
| もっと見る |
EVENT PICKUP
イベント・講座情報

ExhibitionWorkshop2025年5月3日(土)~6月8日(日) 枚方市立御殿山生涯学習美術センター企画展 没後60年記念 矢野橋村展
活動委員会Workshop2025年5月25日(日)13時~15時 ART WORKSHOP 「御殿山で南画を描こう!」
生涯学習美術センターは、市民の皆さんの学習活動・芸術等の文化活動を支援する場所です。

天王寺悲田院町から昭和4年(1929)に御殿山に移転した設立当時の大阪美術学校
御殿山生涯学習美術センターは、かつて枚方市御殿山の小高い山の上にあった「大阪美術学校」の跡地に建設された歴史ある美術センターです。「大阪美術学校」は昭和4年(1929)開校から昭和19年(1944)閉校にかけて、大阪の芸術文化の底上げを図りました。開校当初、大阪美術学校は「芸術の発生地」としての理想を掲げ、矢野橋村(南画家)、福岡青嵐(日本画家)、斎藤与里(洋画家)、近藤尺天(篆刻家)らをはじめ多くの芸術家が設立に関わり、また自ら教鞭を取り芸術の道を切り拓いてきました。
多くの芸術家を輩出した大阪美術学校跡地に、昭和62年(1987)に枚方市立御殿山美術センター(現在、枚方市立御殿山生涯学習美術センター)が設立。美術創作室や設備を構える「市民のアトリエ」として地域に親しまれています。
施設は地階が美術関連書籍の蔵書が豊富な図書館、1階および別棟に4つの創作室、2階がホール等の集会室からなる複合施設です。この図書館を除く1階、別棟、2階部分が、枚方市立御殿山生涯学習美術センターとなっています。
多くの芸術家を輩出した大阪美術学校跡地に、昭和62年(1987)に枚方市立御殿山美術センター(現在、枚方市立御殿山生涯学習美術センター)が設立。美術創作室や設備を構える「市民のアトリエ」として地域に親しまれています。
施設は地階が美術関連書籍の蔵書が豊富な図書館、1階および別棟に4つの創作室、2階がホール等の集会室からなる複合施設です。この図書館を除く1階、別棟、2階部分が、枚方市立御殿山生涯学習美術センターとなっています。
Instagram
まなびのタネ
楠葉・津田・菅原・御殿山 生涯学習市民(美術)センター 公式インスタグラムアカウント
~イベント情報発信中!~
SNS
御殿山生涯学習美術センター 公式SNS
FACILITIES
施設一覧
楠葉
〒573-1118
大阪府枚方市楠葉並木2-29-5
大阪府枚方市楠葉並木2-29-5
津田
〒573-0121
大阪府枚方市津田北町2丁目25-3
大阪府枚方市津田北町2丁目25-3
菅原
〒573-0163
大阪府枚方市長尾元町1-35-1
大阪府枚方市長尾元町1-35-1
御殿山
〒573-1182
大阪府枚方市御殿山町10-16
CONTACT
お問い合わせ
050-7102-3135
開館時間:午前9時~午後9時まで(日曜、祝日は午後5時まで)
休館日:毎月第4月曜日(祝日の場合は開館)・年末年始
住所:〒573-1182 大阪府枚方市御殿山町10-16